【講演会&報告会】発掘から創作へ-考古学が拓く表現の世界-(明治大学博物館)

遺跡発掘の体験を漫画で発信している漫画家、今井しょうこさんの講演会へ行ってきました。
ワイが遺跡の発掘の仕事を始めるにあたり、何か良さげな本はないかと検索したところ、おすすめで最初に出てきたのが、今井さんの漫画「漫画でわかる考古遺跡発掘ワークマニュアル」、漫画ならとっつきやすいだろうということで、とりあえず手にした一番最初の本がコレ。
以前、明治大学博物館でたまたま見かけた講演会の案内。せっかくなら見かけたのなら、何かのご縁ということで参加したのだけれど、遺跡発掘の話だけでなく、そこから生まれた創作の話なども聞けて面白かった。
因みに、講演の内容は、考古学や発掘の魅力、漫画家になったきっかけ、漫画制作の苦労話などについてでした。
考古学や発掘の魅力

今井さん曰く、遺跡の発掘の仕事を始めた理由は、ズバリ「生活(お金)」のため、うん潔い、笑
漫画にも描いてあったけど、仕事を探してハローワークへ行ったところ、そこで募集していたのが、遺跡発掘のお仕事だったのだそう。
遺跡の発掘って、大学や国の専門機関が研究のためにやっているっていう印象があったけど、実は研究のための発掘だけでなく「宅地などの土地整備に伴って遺跡が出てきてしまったので、記録に残しておかなくてはいけない(法律で決まっている)」ってことで行われる発掘がほとんど、なので、実はまだ見ぬ遺跡が全国各地に眠っていたりする。
実際、遺跡を発掘するということは、それまで封印されていた遺跡を壊すということだから、必要に迫れれないのであれば、壊さずにそのまま眠らせておく方が一番の保存方法だしね。

そんな遺跡の発掘の仕事だけど、今井さんが自分が掘った現場で一番印象に残った発掘は、完形の遺物がザクザク出てきた住居。それも1軒だけでなく、同時に5軒だったかな?遺物って掘り上げるころには、壊れていることがほどんどなんだけど、壊れずに残っていたということは、何かしらの意味というか意図がそこにはあったんだろうし、そういうのに思いを馳せるのが好きなんだって。
確かに遺跡発掘を行っていて、住居の構造なんかを先生に説明してもらうのも面白いけど、一番ワクワクする瞬間は「完形の遺物の発見」よね。分かりやすいしインディージョーンズになった気分やわ。
漫画家になったきっかけ

で、そんな今井さんが漫画家になったきっかけは、占い
占いってマジかよって話だけど、大マジで、遺跡の発掘の仕事をしていて、それはそれで生活のための仕事としては十分だったんだけど、何か物足りないと感じていたのだそう。
で、そんな時に、たまたま見かけたインド人の占い師に見てもらったところ「漫画を描きなさい」とのことだったので、自分のやっている遺跡の発掘の仕事を漫画を描き始めて、その漫画を同人誌として出したところ、ある編集者の方の目に留まり、そこから漫画家としてのキャリアが開けたのだそう。
なかなか面白いきっかけだった。
因みに、あとで占い師に「本当に漫画を描くことになった」と報告しに行ったところ、その占い師も別に未来が見えて「漫画を描け」と言ったわけではなく、遺跡の発掘の仕事を「漫画で描くのが面白そうだからすすめただけ」だったそうな。占いじゃなくて、ただのアドバイスで草

でも、今の時代は昔と違って、漫画にしても小説にしても音楽にしても「自分で発信して、それが仕事になる時代になった」というのが、一番大きなことだったんだと思う。
そしてそれは、考古学の専門家でもなく、一素人の目線で描いたことであっても、コンテンツとして面白くて成立するのであれば別にOKなんだよね。要はそれをやるかやらないかというだけの話だったりする。もちろん、キャリアにつながる出会いも必要なんだろうけど。
漫画制作についてなど

漫画制作についてなんだけど、漫画を描く際に注意している点があって、それは「本物じゃないけれど、本物っぽく描くこと」なんだそうな。
どういうことかというと、例えば漫画に描かれている土器、土器も写真だとかそういうのには著作権があったりして、それをそのままを描いてしまうと、権利に引っかかってしまうことがあるらしい。とはいえ、描く土器も本物に則したものにしなくてはいけない。そうじゃないと偽物になってしまう。
なので、本物ではなく偽物なんだけど「ちゃんと本物に見えるように描かなくてはいけない」というのが結構大変らしい。確かに、土器って細かい描写が時代を表したりするから大変そうだなって思った。
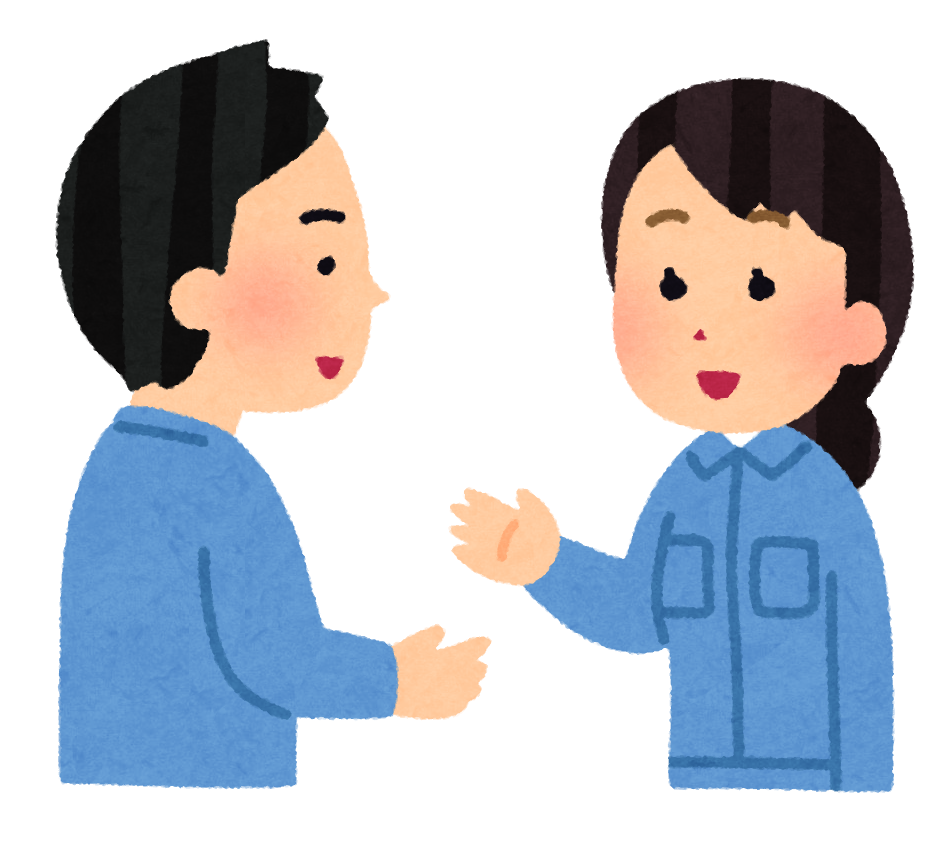
あとは、漫画かならではのネタ、発掘の仕事の後に家で一人で漫画を描いていると「これって本当に面白いのかなぁ」って思うことがあるのだそう。でも、発掘の仕事に行くと、そこには考古学の専門家の先生がいて、同じ発掘の仕事をする同僚がいて、いろいろな発見もあって、話をしているだけで、ネタのきっかけが手に入るのが楽しいと言っていた。
確かに「情報発信」って、漫画でもなんでもインプットって大事なんだよね。自分で体験したことや感じたことが話のネタになるわけだから、そういう意味では「週3日発掘の仕事をして、そこで体験したことを漫画にするという流れ」は、良いサイクルだなと思った。
とまぁ、そんな感じで、たまたま見つけて参加した講演会だったけど、発掘だけでなく、そこから広がる創作の話など、面白い話が聞けて良かった。
